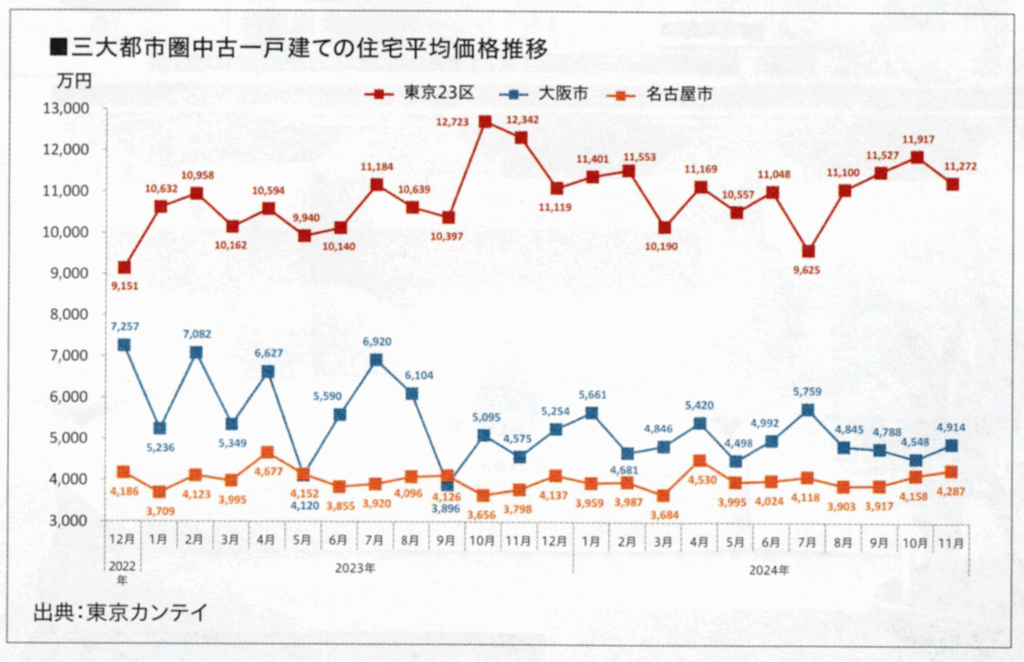2025年、いわゆる「団塊の世代」と呼ばれる1947〜49年生まれの人々が、ついに全員75歳以上を迎える。このタイミングで相続の増加や空き家の増加が加速し、不動産価格の下落が懸念されている。これが、今注目されている「2025年問題」だ。
■ いきなりの暴落は考えにくい
ただし、「2025年になった瞬間に不動産価格が大暴落する」といったシナリオは現実的ではない。というのも、少子高齢化の進行は突然の出来事ではなく、長年にわたって徐々に進んできた社会現象だからだ。不動産市場もすでにその影響を受け始めており、一部では価格調整も見られている。
■ 表と裏──バブルのような都市部と、静かに進む空き家問題
近年、「億ション」や「不動産バブル」など、都心部を中心とした景気の良いニュースが目立つ一方で、地方を中心に空き家は着実に増加している。
2024年に発表された5年に一度の「土地・住宅統計調査」によると、2023年10月時点で全国の空き家数は約900万戸に達し、空き家率は13.8%と過去最高を記録した。
■ 価格を左右するのは需要と供給のバランス
不動産価格は、基本的に「欲しい人(需要)」と「売りたい数(供給)」のバランスで決まる。人口が減少し、供給過多となれば、価格が下がるのは自然な流れだ。
特に、地域差は顕著だ。たとえば、空き家率が最も高いのは和歌山県と徳島県で、どちらも21.2%。一方で、埼玉県や沖縄県は10%を下回っており、地域ごとの事情は大きく異なる。
■ 立地が命──「どこにあるか」が資産価値を決める
同じ都道府県内でも、エリアによって空き家率は大きく異なる。つまり、これからの不動産選びでは「どのエリアにあるか」がますます重要になってくる。
今後、人口減少が進む地域では、不動産価値の大幅な下落も予想される。そうした地域では、「立地適正化計画」という街をコンパクトに再編する取り組みも始まっている。これは、行政サービスやインフラを効率化するために居住エリアを集中させようという施策だ。
■ 自治体の選び方が未来を変える
このように、今後の不動産価値は「どの自治体に住むか」が大きなカギとなる可能性が高い。街の魅力、インフラ整備、行政の方針によって、同じ地域でも明暗が分かれる時代がすぐそこまで来ている。